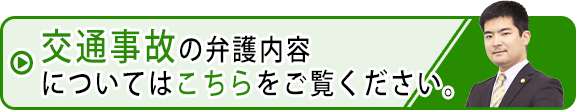過失運転致死傷罪とは
1 過失運転致死傷罪とは?
自動車を運転する際は、当然ですが歩行者などの他人を死傷させないように細心の注意を払う必要があります。
近年では、車の安全制御技術の向上により交通事故の件数自体は減少傾向にあるものの、依然としてドライバーには慎重な運転が求められます。
自動車の運転中に他人を死傷させてしまった場合、自動車運転処罰法にある「過失運転致死傷罪」に問われてしまう可能性があります。
まずは、過失運転致死傷罪に関する基本的な事項として、根拠法・成立要件・法定刑を確認しておきましょう。
⑴ 過失運転致死傷罪の根拠法
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転処罰法)5条を根拠としています。
通常の刑法でも、業務上必要な注意を怠って他人を死傷させる犯罪類型として、「業務上過失致死傷罪」が規定されています。
自動車の運転による過失傷害・致死も、元々は業務上過失致死傷罪として処罰されていました。
しかし、悪質な交通違反を特に重く処罰する観点から、平成19年の刑法改正以降、「過失運転致死傷罪」として自動車運転処罰法に括り出され、法定刑が加重されています。
⑵ 過失運転致死傷罪の成立要件
過失運転致死傷罪の成立要件は以下のとおりです。
・自動車の運転上必要な注意を怠ったこと(過失)
・他人を死傷させたこと
・過失行為と死傷の結果の間の因果関係
過失行為には非常に様々なパターンがあります。
例えば、わき見運転などの前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどが考えられるでしょう。
⑶ 過失運転致死傷罪の法定刑
過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
ただし、傷害が軽い場合には、情状により刑を免除できるとされています。
2 過失運転致死傷罪で逮捕されるとどうなる?
⑴ 逮捕の要件
一般的に、逮捕(身体拘束)の要件は以下の2つとされています。
①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法199条1項)
捜査機関が被疑者を逮捕するためには、被疑者に対する嫌疑がある程度以上に固まっていることが必要です。
過失運転致死傷罪の場合では、被害者を死傷させた車の運転者が被疑者であるということが確実であれば、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」は認められるでしょう。
②逮捕の必要性
被疑者が罪を犯したことが確実であるとしても、必ず逮捕されるというわけではなく、捜査が在宅で進められる場合もあります。
そもそも被疑者を逮捕する目的は、罪証の隠滅と逃亡を防止するということにあります。
したがって、逮捕の必要性については、罪証の隠滅と逃亡のおそれがどの程度あるかを考慮して判断されます。
さらに、犯した罪が重大であればあるほど、一般的に逮捕の必要性は高まると考えられます。
同じ過失運転致死傷罪であっても、被害者が死亡してしまった場合や、交通違反の程度がひどい場合などは、罪証の隠滅と逃亡のおそれが類型的に高いといえますので、逮捕の可能性が高くなるでしょう。
⑵ 逮捕の後は勾留に移行
被疑者が警察に逮捕された場合、送致から24時間以内、かつ逮捕の時から72時間以内に、検察官が裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留とは、簡単にいえば身柄拘束の延長です。
逮捕は72時間までしか継続できないのに対して、勾留は勾留請求の日からさらに最大20日間、被疑者の身柄を拘束し続けることができます。
なお、勾留の必要性がないという理由で勾留請求が行われない場合や、裁判官により勾留請求が却下される場合もあり、勾留が行われないこととなった場合には、その時点で被疑者の身柄は釈放されます。
ただし、その後在宅での捜査が継続する場合が通常で、事件が完全に終了したわけではありませんので注意が必要です。
放置して弁護士に刑事弁護を依頼しないでいると、起訴され前科がつく可能性もあります。
⑶ 検察官による起訴・不起訴の判断
起訴前勾留の期間内に、検察官は被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
どのような場合に起訴されるのか、また不起訴を得るための方法などについては、後で解説します。
⑷ 起訴後の勾留と保釈
検察官により被疑者が起訴された場合、被疑者は引き続き身柄を拘束されます。
これを「起訴後勾留」といいます。
起訴後勾留の期間は原則2か月ですが、1か月ごとに何度でも延長することが可能です。
したがって、身柄拘束されたまま過失運転致死傷罪で起訴されてしまったら、身柄拘束が相当長い期間継続することを覚悟しなければなりません。
ただし、起訴後勾留の段階では、被疑者は保釈の請求をすることができます。
保釈は通常、弁護士が弁護人として請求し、一定条件を満たした場合に、金銭を担保として身柄拘束を解くものです。
3 過失運転致死傷罪で起訴されるケース
過失運転致死傷罪に限らず、すべての犯罪について、起訴するかどうかの判断は検察官の裁量に委ねられています。
検察官は、どのような基準で起訴・不起訴の判断を行っているのでしょうか。
⑴ 起訴の判断基準
検察官が被疑者を起訴するためには、被疑者が罪を犯したことが確実であるといえなければなりません。
もし被疑者が本当に罪を犯したのかどうか分からない場合(真犯人が別にいる場合や、被疑者の行為が犯罪の要件を満たさない可能性がある場合など)には、嫌疑不十分で不起訴となります。
一方、被疑者が罪を犯したことが確実であっても、常に起訴されるとは限りません。
刑事訴訟法248条は、以下のとおり規定しています。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
(刑事訴訟法248条)
このように、検察官は一切の事情を総合的に考慮し、罪を犯した被疑者を不起訴にする場合があります。
これを「起訴猶予」といいます。
自動車の運転によって他人を死傷させてしまったこと自体が事実である場合には、被疑者から弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官に起訴猶予処分を下してもらえるように活動することになります。
⑵ 不起訴になるための弁護活動|謝罪・被害弁償
過失運転致死傷罪での起訴・不起訴の判断においては、犯罪行為と結果の悪質性や、被疑者本人の前科などがかなり影響します。
これらの事情は、被疑者の努力で後から変えることはできないものです。
しかし、被疑者が逮捕後でもできる、良い情状を得るための努力として、「犯罪被害の回復」があります。
過失運転致死傷罪の場合には、具体的には、被害者に対して謝罪と被害弁償を行うことが有効です。
ただし、被疑者が逮捕されている場合には、被疑者自ら謝罪と被害弁償を行うことはできません。
また、仮に被疑者自らが謝罪に行くことができても、当事者同士のやり取りは更なるトラブルを招いてしまう可能性があります。
そのため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者に連絡を取り、被害弁償についての交渉を行うことをおすすめします。
4 過失運転致死傷罪の判例
過失運転致死傷罪は、傷害が軽いケースであれば刑が免除されることもあります。
また、刑が免除されない場合でも、略式起訴による罰金刑に留まるなど、比較的軽い刑罰で済むケースも多いところです。
しかしながら、悪質なケースや被害が死亡など重大なケースでは、初犯であっても実刑を免れない場合もあります。
最後に、最近の裁判例を参考に、過失運転致死傷罪で起訴された場合の量刑について見ていきましょう。
⑴ スマホゲームによる前方不注意の死亡事故
名古屋地判令和2年3月23日{初犯・禁錮(現:拘禁刑)1年4か月・実刑}
運転者がスマートフォンのゲーム画面に気を取られるあまりの前方不注意により、85歳の歩行者を撥ねて死亡させた事件です。
この事件では、単なる一時的なわき見との場合と比べても、スマートフォンのゲームに気を取られながら運転するという行為の危険性は大きいと判断されました。
加えて、被害者の死亡という重大な結果が発生したことも考慮され、初犯ながら禁錮1年4か月の実刑判決が下されました。
⑵ アクセルとブレーキの踏み間違いで3名死亡・7名負傷
福岡高判令和2年2月14日{初犯・禁錮(現:拘禁刑)5年6か月・実刑}
アクセルとブレーキの踏み間違いによって、時速86キロまで加速させた自動車を病院のラウンジに突入させ、3名死亡・7名負傷の結果を発生させた事件です。
この事件では、ブレーキを的確に操作して安全に停止するという運転者としての基本的な注意義務に違反したこと、行為の危険性の高さ、被告人に結果回避可能性があったことなどが指摘され、被告人の過失は重大であると認定されました。
その上で、3名死亡・7名負傷というきわめて重大な結果を発生させたことについて、過失運転致死傷罪の事案の中でも特に重い刑事責任を負うべきとされ、初犯ながら禁錮5年6か月の実刑判決が下されました。
交通事故による犯罪について私選弁護人を依頼するメリット 飲酒運転で刑事逮捕されてしまったら